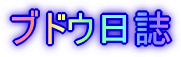 (2011年6月)1月〜 5月 6月 7月 8月 9月 10月〜 ) ブドウ歴史 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 棚づくり
(2011年6月)1月〜 5月 6月 7月 8月 9月 10月〜 ) ブドウ歴史 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 棚づくり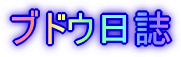 (2011年6月)1月〜 5月 6月 7月 8月 9月 10月〜 ) ブドウ歴史 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 棚づくり
(2011年6月)1月〜 5月 6月 7月 8月 9月 10月〜 ) ブドウ歴史 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 棚づくり
| 月日 天気 |
作業項目 | 日誌 | サムネール写真 |
| 6/1〜6/7 | 花穂づくり | 花穂が大きくなり、花の枝がきれいに分かれてきたので、ジベレリンに先がけて花穂づくり。一番上の両側の枝2本のこし、上から5,6段を切って、下のほうだけ残した。大体13段もあればいいというがなかなかそこまでカットはできず、15〜20段ぐらい残っているかもしれない。 また一番下側はカットしていない。 毎日こまめに誘引を繰り返し、やっと棚全体に広がってきた。緑のカーテンでリビングはとても涼しい。 |
|
| 6/3 6/5 6/7 | |||
| 6/8〜6/10 | 摘心 脇芽摘み 巻ひげとり 消毒 ジベレリン1回目 |
6/6 花のほんの少しの部分咲き始めた。天気のいい日が続くので、あっという間に咲き出すと思う。 6/8 花のほとんどが咲き出した。枝が1m以上伸びてきたものが多く、一番先を摘心し始めた。 6/102回目の消毒。(オルトラン350倍プラストリフミン2000倍?) 夕方 ジベレリン1回目 半分以上行う。(明日は雨の予定なので、急きょ実行。)いい天気が続き、ほとんどの花の先のほうまで咲き始めた。指で房をはじくと茶色くなった殻がはじけてどんどん落ちる。 葉をよく見ていると、病気の気配のする葉がたまにある。 |
|
| 6/8 6/10 6/10 6/10 | |||
| 6/12 | 残り半分の ジベレリン処理 |
6/10日に行わなかった分のジベレリン処理。 結局 水溶液2l(粉末一袋5mg入り)を作った。花柄が葉に落ちると、葉が汚れて、その部分から細菌が付きそう。 花房はできるだけ、棚の下側に早くおろし、花の殻やおしべが葉の上に落ちないようにすること、またそんな葉を見つけたらできるだけ早くふるい落とすこと。花房の数はざっと200余り。まだほとんどの花はつけっぱなし。 |
|
| 6/12 6/12 6/12 | |||
| 614〜16 | アメリカシロヒトリ 黒痘病の始まり |
お天気のいい日が続き、花殻やめしべが順調に落ちて綺麗になっていく。 隣の柿から移ったのかアメリカシロヒトリの付いた葉があった。幼虫がびっちり。すぐにカットし、踏み潰す。葉には黒痘病の葉がそろそろ出てきた。 棚に寝ている蛇。このころに3度蛇に遭遇 |
|
| 6/14 6/16 6/16 6/16 |
|||
| 6/17〜21 | ジベレリン2度目 | 摘房を進めていく。一日に20〜30房。まだ140近くある。やっぱり300房くらいあったのかもしれない。 粒もまだまだ多すぎる。 一回目のジベレリンから10日だが、実がかなり大きくなったし、天候の都合もあって、21日(一回目から丸10日) ジベレリン2回目。摘粒を進めながら傘もかけた。ジベレリンは5mを2lに薄め、1,8l入りの醤油用ペットボトルの底を切り抜き、上のキャップをきっちり締め、取っ手を持ってつけていった。置くときは細長い植木鉢にはめ込んで安定させた。 |
|
| 6/17 6/19 6/21 | |||
| 6/22〜25 | スミチオン+トリフミン消毒 | 22日の朝、明日から天気が梅雨模様になるとのことで、朝からスミチオンとトリフミンで消毒。実にはできるだけ消毒液が掛からないように、傘の上にスプレーの上を持っていくように気を付けた。後の半分は2階の窓からシャワーのようにかけた(これだけでは葉の裏側にはかからない。 黒痘病がだんだん始まってきた。 |
|
| 6/22 6/22 6/23 6/23 | |||
| 6/23〜 | 梅雨入り | 22日の晴天を最後に梅雨空が続く。 摘房を一応止めて、黒痘病などトラブル粒を見つけ次第カットすることに。今のところ(26日)一日10数個ぐらいの黒痘病が見つかる。そのほかに裂果もある。 |
|
| 6/24 6/26 | |||
ブドウ歴史 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 棚づくり 2012 home 実育て日記