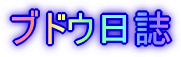 (2011年7月)1月〜 5月 6月 7月 8月 9月 10月〜 ) ブドウ歴史 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 棚づくり
(2011年7月)1月〜 5月 6月 7月 8月 9月 10月〜 ) ブドウ歴史 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 棚づくり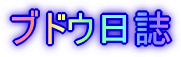 (2011年7月)1月〜 5月 6月 7月 8月 9月 10月〜 ) ブドウ歴史 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 棚づくり
(2011年7月)1月〜 5月 6月 7月 8月 9月 10月〜 ) ブドウ歴史 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 棚づくり
| 月日 天気 |
作業項目 | 日誌 | サムネール写真 |
| 7/1〜 7/4 |
7/1 スミチオン+トリフミン 消毒 |
アメシロの被害がそろそろ広がってきた。ブドウにも一枚付いたものがあった。 7/2 ,7/3 白根にブドウ農園見学。(下記に別記) 4日、120房以降、摘房をしていないので、思い切って、各房の上部10個くらいずつ摘粒した。 |
|
| 7/2 7/2 7/4 |
|||
| 7/7〜 7/10 |
房のカット ジベレリン焼け |
蒸し暑いが雨はあまり降らない。梅雨真っ只中のはずだが、それほど降らない。 黒痘病の粒は見つけ次第カット、一日10〜20個ほど。 7日にカットlした房。ジベレリンなどしていない自然に放ってあった房。親子(大きくなった粒と小さな粒が混じる状態)の粒と黒痘病が発生している。 10日にカットした房。最初からカットするつもりだったが、粒も大きく立派だったので、ここまで育ててしまった。密集し過ぎ。 右の上の粒はジベレリン焼けしたもの。 あまりひどくはないが、いくつかの房に数個見られる。 |
|
| 7/7 7/7 7/10 7/10 | |||
| 7/11 |
晩腐病発生? | 捕まえた青虫。蛾の幼虫だろうか?時々見かけるようになった。 真ん中は房の上のほうについた晩腐病?の粒。5.6個固まってあった。見つけ次第切り取り。2か所あったが、ほかの発生は今のところない。 ブドウスカシバが入った葉の茎。枝にも入った部分があったので、スミチオン注入。 |
|
| 7/11 7/11 7/11 |
|||
| 7/14 | スミチオン+トリフミン で消毒 |
7/14 カナブンが昨年より早く大量発生。葉を食い荒らし始めた。 スミチオンが効くとのことで、普段より濃い消毒液(スミチオン500倍)を作り、2階の窓から、ブドウの葉の表のみにかかるように丁寧にかけた。 実にはまったくかからなかったと思う。 カナブンが数十匹と青虫が10匹ほど落ちて死んでいた。 緑のカーテンが今年も涼しい。 |
|
| 7/14 7/15 7/15 7/15 |
|||
| 7/16 | 紙の袋掛け | 7/16 100枚紙の袋を購入(農協 たぶん480円) 100枚のみ架け替える。残りはポリエチレンの袋のまま ポリの袋は18枚あったので全部で118個。 ぱっぱの隅が枯れるのが見えてきた。おかしな葉っぱはできるだけとってします。 実は毎日ぐんぐん大きくなっている |
|
| 7/16 7/20 7/21 | |||
| 7/22 〜24 |
防ちょうネット取り付け | 穏やかな曇りの日を選んで防ちょうネットを全体にかけた。(22〜23日) 腰痛がひどい時期で結構大変だった。7×9mの大きな網を真中東西にとおし、広げたが、南西部分が足りず、下部のみ別のネットで覆う。 22日ごろから心なしか色づき部分が見られるようになった。 |
|
| 7/22 7/23 7/23 7/24 | |||
| 7/26 〜31 |
色づき始め | 少しずつ色づきがはっきりしてきたが、やはりつけすぎの傾向で、とび玉の出る色づきではない。全体的にあるいは一部のみ色が変わってくる傾向。 袋の中でだんだんブドウの大きくなっていく様子が、紙の張り具合でわかる。 |
|
| 7/26 7/31 7/31 |
![]()
7月3日白根にあるブドウ作りを専門にしている果樹農家のハウス栽培を見学した。
名前を聞くのを忘れたが(惜しい!!)ハウスの中に入れていただいて、いろいろと助言をしてもらった。
ここにまとめておく。
・黒痘病の予防について、
芽吹き前、本来なら2000倍ぐらいに薄めて使う「ベンレート」を200倍くらいの濃い濃度にして、
スプレーでもいいが刷毛で丁寧に塗っていくとなおよい。(ネットでも調べ済。
ベンレート 2000倍 収穫45日前まで 3回まで
トリフミン 2000倍 収穫7日前まで 3回まで
(おじさんの話ではトリフミンはうどんこ病に良く効くとのこと。一番の予防は芽吹き前の消毒。
保護のためにメガネ、マスクを忘れないこと。)
形のよいブドウを作るには

形の良いブドウを作るには
ジベレリン処理をする際に最も下の部分3.5センチをのこし 後の14〜5段は全部指でそぎ落とす。
大きな粒にするために・・摘粒。。30〜多くても40.50個 出来は約500gぐらいまで
一坪に約15房 専門家で約18房ほど。
(我が家は約5坪 75〜90房ぐらいがよい。)
巨峰の場合は花が咲く時期で約1mの枝の長さがいる。 この点では合格。
葉も実が大きくなる過程の時期は少し多めにつけておく。(少し暗い位でもいい)
収穫が近くになるにつれ、葉っぱを掻きとって少なめにしていき、ブドウに直接陽が当たるようにする。
(真夏になると病気が出なくなるので、袋も傘も?いらない)
地熱を上げないために、本当はある程度の草が生えているくらいのほうがいい。
地熱が上がると根が深く下がっていく。
樹勢を抑えるためには根切しかないとのこと。 幹を中心に一m位のところを掘って大きな根があったらのこぎりで切る
(とてもできそうにないが・・・)
虫予防が他で可能なら、古皮剥ぎはしないほうがいい。
ブドウの新しい品種でおいしい一押し「ウインク」
11月10日ほどに出荷の遅い品種。ただし、かなり手がかかる。とのこと。摘粒などに。
ブラックオリンピアがもう黒く色づいていた。レッドオリンピアも色づき始め。
マスカットも味見をさせてくれたが、もうそろそろ食べられるようになってきていた。
近所の農園より群を抜いて立派なブドウ、いろんな種類を作っていられたが、
ハウス栽培のためにまだ2回しか消毒はしていないとのこと。また肥料は堆肥のみ、化学肥料は一切使わない。
早生の栽培のためにストーブがあった。 鳥対策はかなり慎重。
風通しを良くするために下部と3mぐらいの部分ぐるり全部ネット仕立てになっていたが、
人の出入り時さえ、スズメを入れないように気を使っている。スズメが一番大敵の様。
ビニールハウスの中のブドウはほとんど傘もかかっていず、(一部分笠かけのものはあった)
袋はかけないとのこと。路地ものよりかなり早く収穫できるよう。
よく見ると、裂果しているもの、腐敗(灰色カビ病、晩腐病)の粒も結構あって、その摘粒をされていた。
ビニールは2年しか持たないとのこと。
ブドウは大体全部の種類が直販で一キロ1000円とのこと。
8月終わりから9月1.2日のころ、真っ赤なブドウが一面にできるので、写真に撮りたい時はどうぞとのこと。
11月初旬から「ウインク」出荷。このころにもぜひもう一度訪れたい。
1.jpg) |
1.jpg) |
1.jpg) |
| |
||
1.jpg) |
1.jpg) |
1.jpg) |
| |
||
1.jpg) |
1.jpg) |
1.jpg) |
| |
レッドオリンピア | マスカット |
1.jpg) |
2.jpg) |
1.jpg) |
| 富士稔 |
ウインク | 巨峰 |
ブドウ歴史 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 棚づくり 2012 home 実育て日記
2011((1月〜 5月 6月 7月 8月 9月 10月〜)